確定申告の手続きが複雑で面倒だと感じている人は多くいます。この記事では、確定申告を簡単に済ませるための方法やツール、よくある質問への回答などを解説します。記事を読めば、確定申告の手続きの効率化や、時間と労力の大幅な節約が可能です。
確定申告を簡単に済ませるには、日頃からの必要書類の整理と帳簿付けが重要です。確定申告ソフトやスマホアプリを活用すると、作業時間を大幅に短縮できます。
確定申告とは所得税を計算・申告する手続き

確定申告は個人が1年間の所得と税額を計算し、申告する手続きです。確定申告の基礎知識を、以下の項目に分けて解説します。
- 確定申告と年末調整の違い
- 確定申告が必要な人
確定申告と年末調整の違い
確定申告と年末調整は税金に関する手続きですが、以下の違いがあります。
| 比較項目 | 確定申告 | 年末調整 |
| 対象者 | 自営業者、複数の収入源がある人 | 給与所得者 |
| 実施期間 | 翌年2月16日~3月15日 | 年末 |
| 手続き担当者 | 本人 | 勤務先 |
| 計算対象の所得範囲 | すべての所得 | 給与所得のみ |
| 控除項目の多様性 | 多様(選択肢が多い) | 限定的(確定申告より少ない) |
| 還付金の受け取り方 | 申告後に還付 | 即時還付(多くは12月または1月の給与で調整) |
| 修正の可否 | 可能(更正の請求や修正申告) | 原則不可(確定申告で修正する場合がある) |
| 適用範囲(還付額) | 20万円以上の還付も可能 | 20万円以下の還付に限られる場合が多い |
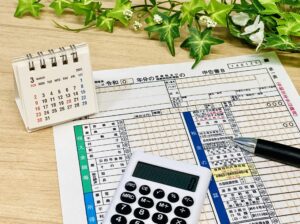
確定申告が必要な人
確定申告の対象となる人の主な条件は、以下のとおりです。
- 給与所得者で年収2000万円を超える人
- 給与を2か所以上から受けている人
- 給与以外の所得が20万円を超える人
- 事業所得(自営業)がある人
- 不動産所得がある人
- 退職所得がある人(特別な場合を除く)
- 譲渡所得がある人
- 山林所得がある人

年末調整を受けていない給与所得者や、所得税の還付を受けたい人も確定申告が必要です。青色申告をする人や、損失の繰越控除を受けたい人、外国で得た所得がある人も確定申告の対象となります。

確定申告の準備を簡単にする方法

確定申告の準備を簡単にする方法は、以下のとおりです。
- 必要な書類をそろえる
- 帳簿を付ける
必要な書類をそろえる
確定申告に必要となる主な書類は、以下のとおりです。
- 源泉徴収票
- 給与所得の支払明細書
- 年金の源泉徴収票
- 保険料控除証明書
- 医療費の領収書
- 寄付金の受領証
- 住宅ローンの年末残高証明書
- 不動産収入の関連書類
- 事業収入の帳簿や領収書
個人の状況によって確定申告に必要な書類は異なるので注意しましょう。マイナンバーカードまたは通知カードや、本人確認書類、還付金受取用の銀行口座情報も準備してください。
帳簿を付ける
正確な帳簿があれば、収入や経費の把握が簡単になり、確定申告がスムーズに進みます。帳簿を付ける際は、日々の収入と支出を漏れなく記録することが基本です。取引を証明する領収書や請求書は、整理して適切に保管する必要があります。記録に基づいた、基本的な帳簿の作成も求められます。
効率的に帳簿を付けるためには、エクセルや会計ソフトの活用がおすすめです。デジタルツールを使えば、入力や集計が簡単になります。帳簿の記入ルールは統一し、一貫性を保ちましょう。経費は分類を明確にし、カテゴリー別に整理すると後々の確認作業が楽になります。
定期的に帳簿の内容を確認し、誤りがあれば修正してください。バックアップを取ると、データの紛失を防げます。帳簿は7年間の保存が求められます。
確定申告の簡単なやり方
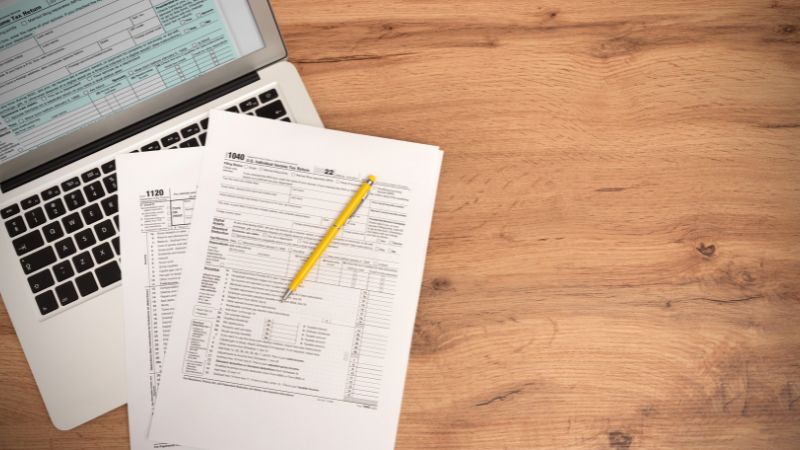
確定申告を簡単に済ませるための方法は、以下のとおりです。
- 申告方法を選択する
- 確定申告書を作成する
- 確定申告書を提出する
- 税金を納付または還付を受ける
申告方法を選択する
自分に合った申告方法を選ぶと、確定申告がスムーズに進められます。主な申告方法としてe-Tax(電子申告)や確定申告会場での提出、郵送、税理士による代理申告から選べます。e-Taxは、インターネット上で確定申告できるので便利です。
確定申告会場での申告は、直接相談しながら進められるメリットがあります。郵送による申告は、自宅で準備して郵便局から送るだけなので手軽な方法です。税理士による代理申告は、専門家に任せられるので安心できます。
確定申告書を作成する

e-Taxソフトや国税庁のウェブサイトで確定申告書を作成します。所得税の確定申告書(A様式またはB様式)を選択しましょう。確定申告書を正確に作成すると、適切な納税や税金の還付が受けられます。収入や経費、控除項目などの情報を入力し、添付書類をスキャンまたは写真撮影します。
情報の入力が完了したら、記入漏れや誤りがないか再確認しましょう。自動計算された税額を確認してください。e-Taxを利用する場合は電子署名を、書面で提出する場合は作成した確定申告書を印刷します。添付書類には源泉徴収票や領収書などの書類があり、申告内容の証明に必要になります。

確定申告書を提出する
確定申告書の主な提出方法は以下のとおりです。
- e-Taxを利用した電子申告
- 税務署への直接持参
- 郵送での提出
確定申告書の提出期限は原則として3月15日までとなります。期限を過ぎると延滞税などのペナルティが発生する可能性があるため、早めの準備と提出を心がけましょう。提出先は納税地を所轄する税務署で、確定申告書と必要書類を添付して提出してください。
確定申告書の控えは必ず保管し、納付書がある場合は一緒に提出します。還付申告の場合は、口座情報も忘れずに記入しましょう。
税金を納付または還付を受ける
税金を納付する場合は、期限内に金融機関や税務署で支払います。税金が還付される場合は、申告から1〜2か月後に指定口座に振り込まれます。納付方法の種類は現金や振込、クレジットカード、電子納税です。税金を一括で支払えない場合は、分割納付の相談も可能です。
e-Taxを利用している場合は、ダイレクト納付で納税できます。税務署から送付される納付書を使用しましょう。税金の納付期限は原則3月15日まで、振替納税の場合は4月中旬となります。e-Taxや税務署で、還付金の進捗状況の確認が可能です。税金の還付が遅れた場合は、還付加算金が付与される場合もあります。
【控除別】確定申告の簡単なやり方

確定申告は、以下の控除の種類によって手続きが異なります。
- 医療費控除
- ふるさと納税
- 住宅ローン控除
医療費控除
医療費控除は、1年間に支払った医療費の一部を所得から差し引ける制度です。医療費控除を利用すると、税金の負担を軽減できる可能性があります。医療費控除を受けるための手順は以下のとおりです。
- 対象となる医療費を確認する
- 関連する領収書や明細書を整理する
- 医療費控除の明細書を作成する
- 明細書の内容を、確定申告書へ記入する
医療費控除の対象となる医療費には、治療費や医薬品代、通院のための交通費などが含まれます。10万円または所得の5%のいずれか低い方を超える部分のみが控除の対象となる点に注意しましょう。確定申告の期限は翌年の2月16日~3月15日までです。
医療費控除は過去5年分まで遡って申告できるため、以前の年の医療費が多かった場合は確認してください。
ふるさと納税
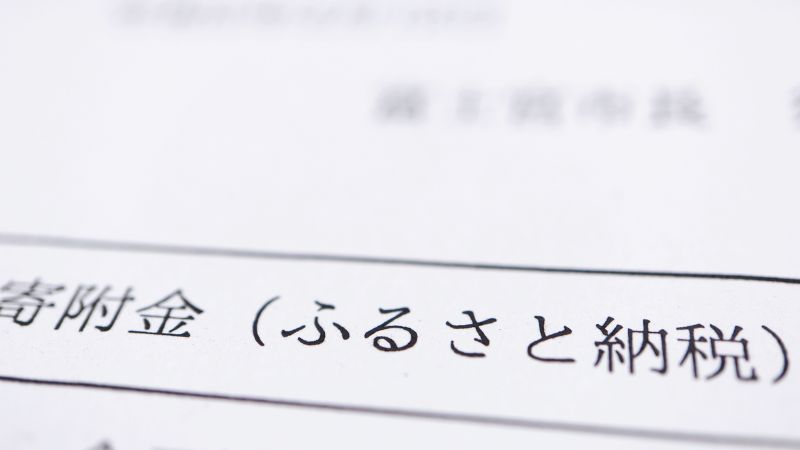
ふるさと納税は、地方自治体への寄附で税金の控除を受けられる制度です。ふるさと納税を利用すると、寄附金の一部が所得税と住民税から控除されます。ふるさと納税の特徴は、寄附先の自治体からの返礼品がある点です。地域の特産品などがふるさと納税の返礼品として選べるので、寄附をしながら各地の名産品を楽しめます。
ふるさと納税を利用する際は、専用のポータルサイトなどで寄付したい自治体や返礼品を選択しましょう。選んだ自治体へ寄付(支払い)し、自治体から送られてくる寄付を証明する書類(寄附金受領証明書など)を受け取ります。受け取った証明書をもとに、税金の控除を受けるための申請をします。
ふるさと納税の控除を受けるには、原則として確定申告が必要です。しかし、給与所得者の場合はワンストップ特例制度を利用すると、確定申告をしなくてもふるさと納税の控除を受けられます。
住宅ローン控除
住宅ローン控除は、住宅ローンを組んで家を購入した人が受けられる税金の控除制度です。住宅ローン控除を利用すると毎年の所得税や住民税が減額され、家計の負担を軽くできます。住宅ローン控除を受けるためには、返済期間10年以上の住宅ローンを利用して住宅を取得、または増改築が条件です。
住宅ローン控除は、住宅に本人が実際に居住している必要があります。控除を適用する年の年末時点で、住宅ローンの残高があることも条件です。控除額は年末のローン残高に応じて計算されますが、上限があるので注意が必要です。住宅ローン控除を受けるためには、1年目に確定申告が必要となります。
2年目以降は、年末調整で住宅ローン控除を受けられます。必要な書類として「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」が重要です。書類は金融機関から発行してもらう必要があります。住宅ローン控除の期間は、原則として10年間となります。
確定申告を簡単にするツール

確定申告を簡単にするツールは以下のとおりです。
- 確定申告ソフト
- スマホアプリ
- 自動記帳機能付きの会計ソフト
確定申告ソフト
確定申告ソフトは初心者でも使いやすく、効率的に申告書を作成できるツールです。入力ガイド機能が備わっており、指示に従うだけで簡単に操作できます。確定申告ソフトは自動計算機能が搭載されているため、複雑な計算をする必要がなく、計算ミスを防げます。
確定申告ソフトは前年度のデータを引き継いで利用できる機能や、e-Taxと連携してスムーズに電子申告できる点も特徴です。国税庁が提供する「確定申告書等作成コーナー」は、無料で使用できる確定申告ソフトです。有料の民間ソフトには、弥生会計やfreeeなどがあります。
クラウド型の確定申告ソフトを使えば、時間や場所を選ばず作業できます。領収書のスキャン機能があれば、書類管理も簡単です。
スマホアプリ

国税庁が公式に提供している「確定申告書等作成コーナー」アプリを使えば、スマートフォン1台で確定申告を完結できます。「確定申告書等作成コーナー」アプリの特徴は以下のとおりです。
- 領収書をスキャンして経費を自動記録する
- 年間の収支を自動集計する
- 控除項目の入力をガイドする
- 申告書を自動作成する
確定申告書等作成コーナーのアプリは、プッシュ通知機能で申告期限をリマインドしてくれるので忘れずに済みます。
自動記帳機能付きの会計ソフト
自動記帳機能付きの会計ソフトは、売上や経費を自動で記録する機能を備えています。スマートフォンで撮影した領収書をもとに、経費を計上できます。銀行口座やクレジットカードとの連携による自動取り込みや、確定申告に必要な書類の自動作成も可能です。
自動記帳機能付きの会計ソフトはAIによる仕訳の提案などの機能もあり、手作業での入力や計算ミスを減らせます。リアルタイムで財務状況を把握できるため、経営判断にも役立ちます。
確定申告を簡単にする際によくある質問

確定申告に関するよくある質問は以下のとおりです。
- 確定申告をしないとどうなる?
- 確定申告を頼むといくらかかる?
- 確定申告の内容を間違えた場合はどうする?
- 確定申告したら得する人はどんな人?
確定申告をしないとどうなる?
確定申告をしないと、通常の税額に15~20%が上乗せされる無申告加算税が課されます。延滞税も加算され、税務調査の対象となる可能性も高まります。確定申告をしないと各種控除が適用されず、税金の還付も受けられません。所得証明が必要となる行政サービスの利用に支障が出たり、ローンの審査で不利になったりします。
意図的な無申告は、刑事罰の対象となるリスクを伴うため注意が必要です。過去の確定申告漏れが後々発覚すると、将来的な税務処理が煩雑になる恐れもあります。
確定申告を頼むといくらかかる?

確定申告を専門家に依頼する場合、費用は申告内容の複雑さや収入規模によって大きく変わります。一般的な相場は2~10万円程度です。確定申告を依頼する費用の目安は以下のとおりです。
| 依頼先 | 費用の目安 |
| 税理士や会計事務所 | 2~10万円 |
| 個人事業主 | 5~20万円 |
| オンライン確定申告サービス | 1,000〜5,000円程度 |
複雑な確定申告や高額所得者の場合は、10万円以上かかる場合もあります。費用を抑えたい場合は、無料の確定申告相談会や税務署での相談サービスを利用する方法もあります。自分で確定申告を対応できれば、無料または低コストで申告可能です。
確定申告の内容を間違えた場合はどうする?
確定申告の内容を間違えた場合、申告期限から5年以内であれば修正申告が可能です。修正申告書を作成し、税務署に提出しましょう。修正申告では、状況によって過少申告加算税や延滞税が課される可能性がある点に注意が必要です。
税務署から指摘される前に修正申告をすると課税が軽減される場合もあります。ただし、故意に所得を隠した場合は重加算税が課される場合があります。
確定申告したら得する人はどんな人?
医療費が高額な給与所得者は、確定申告で医療費控除を受けられます。支払った医療費の一部が戻ってくる場合がある点がメリットです。副業や投資で収入がある人も、確定申告で適切な税金を計算してください。源泉徴収された税金の一部が還付される場合もあります。
以下の人も、確定申告をすると得をする可能性があります。
- 住宅ローンを組んで家を購入した人
- ふるさと納税をした人
- 年の途中で退職した人
- 災害や盗難の被害にあった人
- 寄付をした人
- 学生で給与所得がある人
- 確定拠出年金(iDeCo)に加入している人
- 多額の雑損失がある人

まとめ
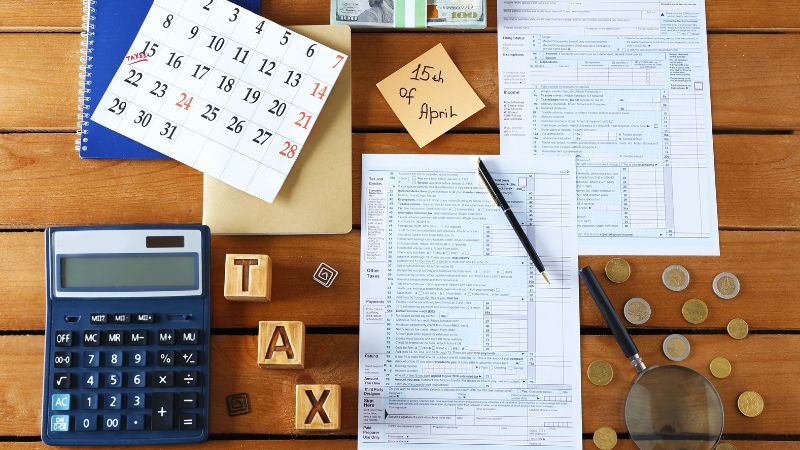
確定申告は、所得を計算して納税額を申告する重要な手続きです。年末調整との違いを理解し、自分が確定申告の必要な人かどうかを確認しましょう。確定申告の準備段階では、必要書類の収集と日頃の帳簿付けが作業を簡略化するポイントになります。確定申告は申告方法の選択や書類作成、提出、納付または還付の順に進みます。
医療費控除やふるさと納税、住宅ローン控除など、各種控除の申告方法も把握しておくことも大切です。確定申告を効率化するツールとして確定申告ソフトやスマホアプリ、自動記帳機能付きの会計ソフトなどを活用できます。確定申告の未申告のリスクや依頼するコスト、修正申告の方法も把握しておくと安心です。
確定申告で得をする人の特徴を理解すると、自分にとってのメリットが明確になります。確定申告の初心者でもポイントを押さえれば、適切かつ簡単に済ませられます。


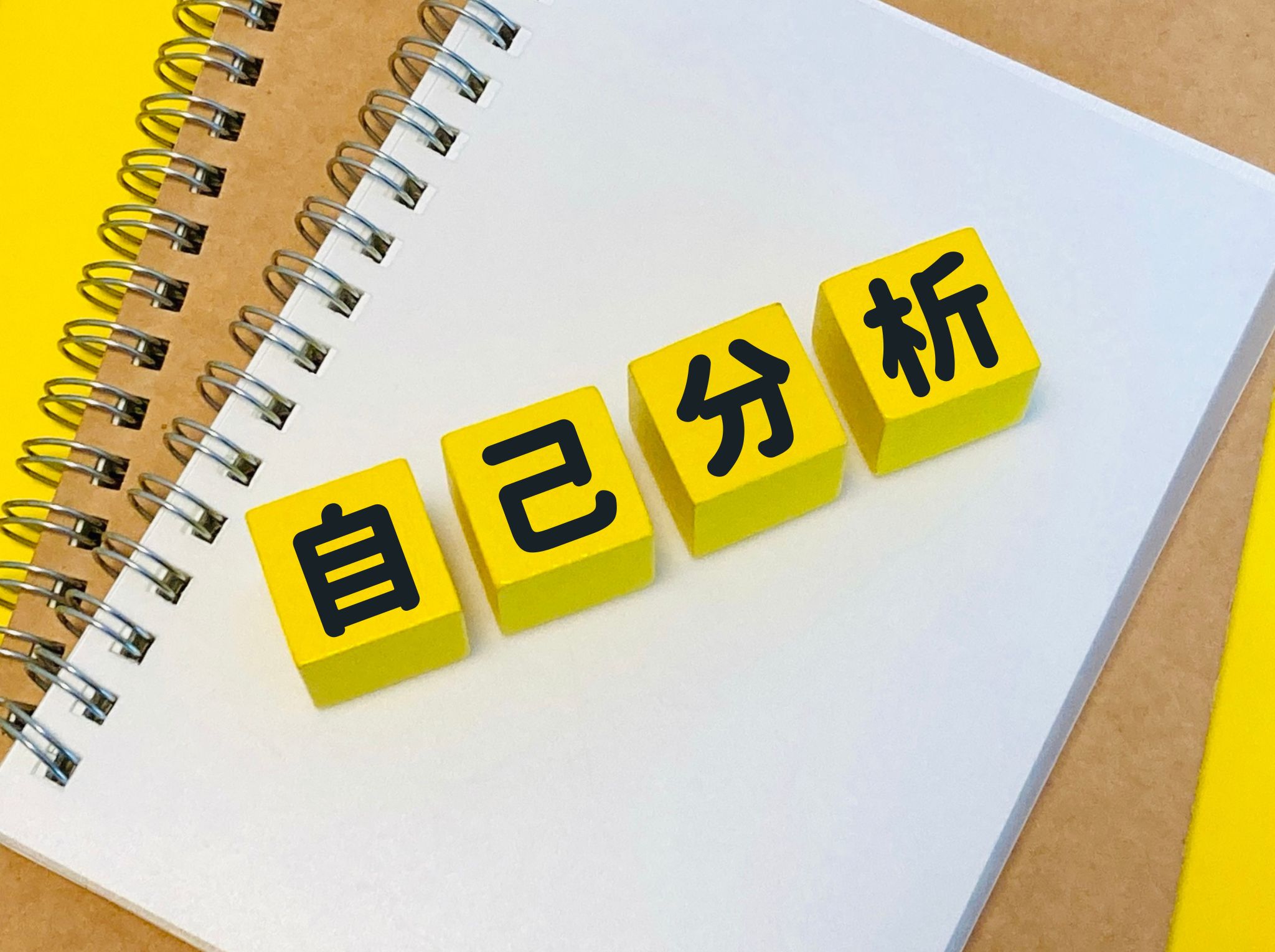











コメント