副業の収入が年間20万円以下なら、確定申告はしなくていいと考える人が多くいます。しかし、住民税の申告や申告が必要なケースもあり、放置するとトラブルの原因になることもあります。
この記事では20万円以下の副業に関する税金の基礎知識や申告の方法、会社にバレないための注意点をまとめました。記事を読めば、副業に関する不安や疑問を解消可能です。

副業の20万円ルールに関する基礎知識
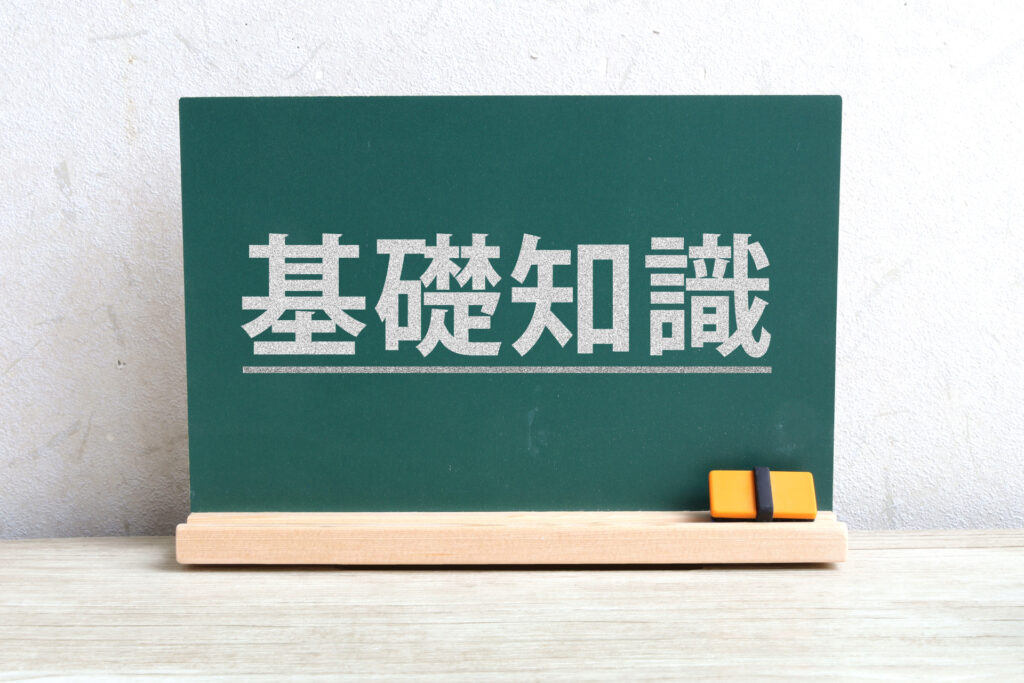
副業における20万円ルールの概要や、適用範囲について解説します。
副業の20万円ルールの概要
副業の所得が年間20万円以下の場合、原則として確定申告をする必要はありません。「所得」とは収入から必要経費を引いた金額です。20万円ルールにより、所得が少ない場合は確定申告を省略できます。
申告が不要になるのはあくまでも所得税の場合です。住民税の申告は別途必要となるケースが多いため、注意が必要です。申告が不要となる条件を理解すると、トラブルを回避できます。
ルールの適用範囲
20万円ルールが適用されるのは、会社員やアルバイトなど給与所得者が副業で得た所得に対してです。フリーランスで得た収入から経費を差し引いて、年間の所得が20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要です。
個人事業主や年金受給者など、給与所得以外が主な収入源である人には適用されません。所得が20万円以下でも、医療費控除や住宅ローン控除などを受けたい場合は確定申告が必要です。適用される対象や条件を理解しておくと、正しい判断が可能です。
副業の所得が20万円以下でも確定申告が必要なケース

20万円以下でも申告が必要になるのは以下の4つのケースです。
- 所得税を納めすぎているとき
- 住宅ローン控除を受けるとき
- 医療費控除を受けるとき
- 副業の不動産経営が赤字のとき
所得税を納めすぎているとき
副業の所得が20万円以下でも、給与所得から天引きされる所得税が多すぎる場合は、確定申告で税金が戻ってくる可能性があります。確定申告をすると、正しい税額にもとづいた計算が行われ、払いすぎた税金の還付を受けられます。一方、申告しないままだと、本来戻るはずの税金を受け取れなくなるため、注意が必要です。
所得が少額でも、納税額に過不足がないかどうか確認し、必要に応じて申告を行うことが重要です。
住宅ローン控除を受けるとき
住宅ローン控除の初年度は、確定申告を行わないと控除を受けられません。副業の所得が20万円以下であっても、申告が必要です。控除を受けると、年間の所得税額を大幅に軽減できます。確定申告を忘れると控除が適用されず、税額が増える可能性があります。
副業の有無にかかわらず、住宅ローン控除を利用する年は確定申告が必要であると知っておきましょう。
医療費控除を受けるとき

年間の医療費が一定額を超えた場合、医療費控除として所得税が減額される制度があります。副業の所得が少なくても、控除を受けたい場合は確定申告が必要です。確定申告をすると、医療費控除により税金が還付されます。
確定申告しなければ控除の権利を失い、自己負担が増えます。医療費が高額になった年は、副業の金額に関係なく、確定申告を検討してください。
副業の不動産経営が赤字のとき
副業で不動産経営をしていて、年間の所得が赤字になることがあります。赤字になったときでも確定申告をすれば、本業の所得と赤字を相殺して、税金を安くできる可能性があります。赤字の申告を行えば、所得税の支払いを抑えることが可能です。赤字額により、還付を受けられる場合もあります。
一方、確定申告をしないと、本来受けられる軽減措置を逃す可能性があります。所得がマイナスであっても、不動産収入がある人は申告の義務やメリットを理解することが大切です。
副業の所得が20万円以下でも確定申告をするメリット

確定申告で得られるメリットは以下の2点です。
- 税金の還付が受けられる
- 税務調査の対策ができる
税金の還付が受けられる
副業の所得が少額でも、必要経費や源泉徴収された税額が多いなら確定申告で税金の一部が戻ってくることがあります。還付金を受け取るには、正しい申告が必要です。確定申告しなければ、払いすぎた税金が戻ってこないため、損をする可能性があります。
少額の副業であっても、確定申告して納めすぎた税金の還付を受けられることを理解しましょう。
税務調査の対策ができる
副業の所得が20万円以下であっても、確定申告をしないと、リスクは低いものの税務署から確認や調査を受ける可能性があります。あらかじめ確定申告をしておくと、適切に処理している証拠を残せます。申告内容が記録に残ると、税務署からの問い合わせにも適切に対応が可能です。
確定申告を怠ると、意図せず申告漏れと判断されるリスクが高まります。確定申告の義務がなくても、自分を守る手段として申告の活用が有効です。
副業の所得が20万円以下の確定申告のやり方

副業の所得が20万円以下でも、確定申告を行うと税金の還付やトラブル回避につながるケースがあります。確定申告の流れを以下の3つのステップに分けて紹介します。
- 必要書類を準備する
- 確定申告書を作成する
- 確定申告書を提出する
必要書類を準備する
確定申告を行うには、まず必要な書類をそろえましょう。必要な書類は、主に以下のとおりです。
- 源泉徴収票
- 副業の収入や経費の記録
- 本人確認書類など
書類をあらかじめ用意すると、申告書の作成がスムーズに進みます。準備が不十分なままだと、申告に時間がかかり、書類の不備によって再提出になる恐れがあります。効率よく手続きを行うために、事前の準備をしっかりと行いましょう。

確定申告書を作成する

必要な書類がそろったら、確定申告書の作成に進みます。申告書に記入する内容は、以下のとおりです。
- 所得金額
- 控除内容
- 納付すべき税額など
国税庁のホームページや会計ソフトを使えば、計算や入力が自動化され、簡単に作成できます。手書きで確定申告を行うと記入ミスのリスクがあるため、電子申告の活用がおすすめです。内容に誤りがないように見直しながら、正確な情報を入力していきましょう。
確定申告書を提出する
申告書を作成したあとは、所定の方法で提出します。提出方法は、以下の3つです。
- 税務署への持参
- 郵送
- e-Taxによる電子申告
e-Taxは自宅から手続きができ、受付の確認もスムーズなため、多くの人に選ばれています。期限内に提出しないと、還付が受けられなかったり、延滞の対象となったりする場合があるため注意が必要です。提出方法を確認し、期限内に手続きを済ませましょう。


副業の所得が20万円以下の確定申告に役立つツール

申告作業を効率化できる、以下の2つのツールを解説します。
- 会計ソフト
- 確定申告アプリ
会計ソフト
副業で発生する収入や経費の管理には、会計ソフトを利用すると便利です。会計ソフトは、取引の記録や仕訳、帳簿の作成を自動で行えます。正確な帳簿が作成できれば、確定申告書の作成もスムーズに進められます。手作業で帳簿をつける場合と比べて、時間やミスのリスクを大幅に減らせるのがメリットです。
副業の記録をしっかり残したい人は、会計ソフトの導入を検討しましょう。
確定申告アプリ
確定申告アプリは、スマートフォンやタブレットを使って申告書を作成・提出できる便利なツールです。操作が簡単で、申告初心者でも安心して使えます。画面の案内に沿って情報を入力するだけで、申告書が自動的に作成されます。紙の申告書に比べて入力ミスが少なく、提出もオンラインで完了するため、手間がかかりません。
時間がない人や手軽に申告したい人にとって、確定申告アプリは強い味方になります。
副業の所得が20万円以下の住民税の取り扱い

住民税の申告に関する以下の2つのポイントを解説します。
- 住民税の申告が必要な理由
- 住民税の申告方法
正しい対応を知っておけば、不要なトラブルや副業が会社にバレるリスクを避けられます。

住民税の申告が必要な理由
副業の所得が20万円以下であっても、住民税は課税対象です。所得が20万円以下でも、自治体に対して申告が必要となる場合があります。確定申告をしていない場合は、住民税の申告を別途行わなければなりません。申告しなければ、本来の所得が自治体に伝わらず、税額の誤りや未納と判断されるリスクがあります。
追徴課税や副業の発覚につながる可能性もあるため注意が必要です。所得税の申告と異なるルールがあることを理解し、住民税についても適切に対応しましょう。
住民税の申告方法
住民税の申告は、各自治体の窓口や郵送、電子申告を通じて行います。住民税の申告に必要な書類は、以下のとおりです。
- 収入の明細書
- 経費の記録
- 本人確認書類など
自治体によって申告期間や提出方法が異なるため、事前に公式サイトでの確認が大切です。適切に申告を行えば、過不足なく課税されて副業に関するトラブルを防げます。確定申告をしていない場合でも、住民税の申告は忘れずに対応するよう心がけましょう。
副業で青色申告が使えるケースとメリット

青色申告は、正しく活用すれば節税につながる便利な制度です。ただし、誰でも利用できるわけではなく、条件を満たす必要があります。副業で青色申告が使える条件と、使うことで得られる以下のメリットを紹介します。
- 副業が事業所得なら青色申告が使える
- 青色申告をすると最大65万円の控除が受けられる
- 青色申告と白色申告の違い
副業が事業所得なら青色申告が使える
副業で青色申告を利用するには、所得の種類が「事業所得」であることが条件です。事業所得とは、継続的に収益を得る目的で、自分の責任と判断で行う仕事から得た収入を指します。アルバイトなどの雇用契約にもとづく報酬は「給与所得」、単発のスキル提供や一時的な副収入などは「雑所得」に分類されます。
青色申告は「事業所得」のみに適用されるため、給与所得や雑所得には利用できません。自分の副業がどの所得区分に該当するかを確認し、必要に応じて税務署に相談すると安心です。
青色申告をすると最大65万円の控除が受けられる

青色申告の条件を満たすと最大65万円の青色申告特別控除が受けられます。控除額が大きいため、税負担を軽減したい副業者にとって有利な制度です。特別控除を受けるための主な条件は以下の2点です。
- 複式簿記による正確な帳簿をつけること
- e-Tax(電子申告)で申告を行うこと
青色申告特別控除は、赤字が出た年の損失を翌年以降に繰り越せます。収入が安定しない副業の初期段階でも、将来的な節税につなげられるのが魅力です。青色申告を始めるには、税務署へ「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
提出期限は、開業から2か月以内または事業開始年の翌年3月15日までです。忘れずに手続きを行いましょう。
青色申告と白色申告の違い
青色申告と白色申告の違いを以下に示します。
| 項目 | 青色申告 | 白色申告 |
| 特別控除 | 最大65万円の控除あり(条件付き) | なし |
| 記帳の方法 | 複式簿記による記帳が必要 | 単式簿記(簡易な帳簿付け) |
| 損失の繰越 | 最大3年間可能 | 不可 |
| 家族給与 | 条件を満たせば必要経費にできる | 原則として経費にできない |
| 申請手続き | 「青色申告承認申請書」を事前に提出 | 申請不要で提出可能 |
青色申告と白色申告では、節税効果だけでなく、活用できる制度や求められる準備が異なります。青色申告は、副業の規模が大きいほど有利です。白色申告は記帳が簡単です。白色申告は手続きに手間がかからない反面、税制上のメリットは限られます。
青色申告でも複式簿記が難しい場合は、簡易帳簿(単式簿記)による記帳が可能です。ただし、控除額は10万円までになります。
副業の所得が20万円以下の際によくある質問
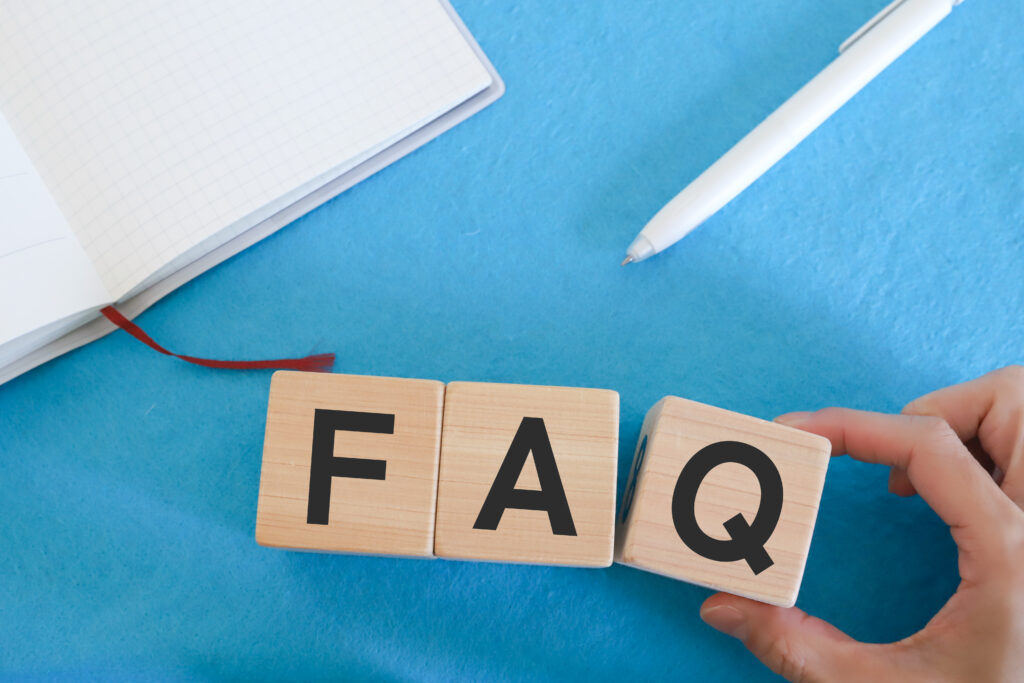
副業の所得が20万円以下の際によくある質問をまとめました。よくある質問は以下のとおりです。
- 副業の経費はどこまで認められる?
- 確定申告をすると副業が会社にバレる?
副業の経費はどこまで認められる?
副業で得た収入に対しては、必要経費を差し引いた金額が課税対象となります。経費とは、副業に直接関係する支出を指します。業務で使う道具や通信費などが該当しますが、私的な支出は経費として認められません。
経費と認められるかどうかの判断が甘いと、申告内容に問題が生じ、税務署から指摘を受ける可能性もあります。適切な帳簿をつけて、根拠のある経費だけを申告することが大切です。
確定申告をすると副業が会社にバレる?
確定申告をすると会社に副業がバレるのではと不安になります。しかし、確定申告をする際、住民税の取り扱いに注意すればリスクを抑えられます。住民税の徴収方法がポイントです。確定申告の際に「自分で納付」を選択すれば、住民税の通知が会社に届くことはありません。
「特別徴収」にすると、会社経由で住民税が引き落とされ、副業の存在が知られる可能性があります。会社に知られたくない場合は、申告書の記入方法を正しく理解し、住民税の納付方法に注意しましょう。
まとめ

副業の所得が20万円以下であっても、確定申告や住民税の申告が必要となるケースがあります。ルールを正しく理解していないと、税金トラブルや会社に副業が知られるリスクもあるため注意が必要です。
申告の有無や方法は状況によって異なります。自分に当てはまるケースを確認したうえでの適切な対応が大切です。ツールの活用や基礎知識の習得により、安心して副業を継続するための環境を整えましょう。
住民税の取り扱いや経費の判断は誤解が多いため、税務署や自治体の公式情報を確認しながら対応すると安心です。副業で得た収入を正しく管理し、将来に向けた資産形成につなげていきましょう。













コメント