個人事業主として独立するには「開業届」の提出が必要です。開業届を初めて提出する場合、必要書類や記入方法に戸惑う人が多くいます。この記事では、開業届の提出に必要なものや記入方法、提出方法を紹介します。記事を読めば、初めての方でも安心して開業届の提出が可能です。
開業届をスムーズに提出して個人事業主としての順調なスタートを切りましょう。

開業届の提出に必要なもの

開業届提出時には、他の書類もあわせて税務署へ提出する必要があります。提出書類に不備があると、開業届が受理されないことがあるため事前にしっかりと準備しましょう。開業届の提出時に必要なものは、下記のとおりです。
- 本人確認書類
- マイナンバー確認書類
- 印鑑
本人確認書類
開業届を提出する際には、本人確認書類の提出が欠かせません。本人確認書類として有効なものは、下記のとおりです。
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- パスポート
- 健康保険証
- 在留カード
- 特別永住者証明書
開業届に添付する本人確認書類は、必ず有効期限内のものを使用してください。開業届を税務署の窓口に直接提出する場合は、本人確認書類の原本が必要です。郵送で開業届を提出する場合は、本人確認書類のコピーを同封しましょう。代理人が開業届を提出する場合は、委任状と代理人の本人確認書類も準備してください。
引っ越しなどで住所変更がある場合は、新しい住所が記載された本人確認書類を用意しましょう。
マイナンバー確認書類
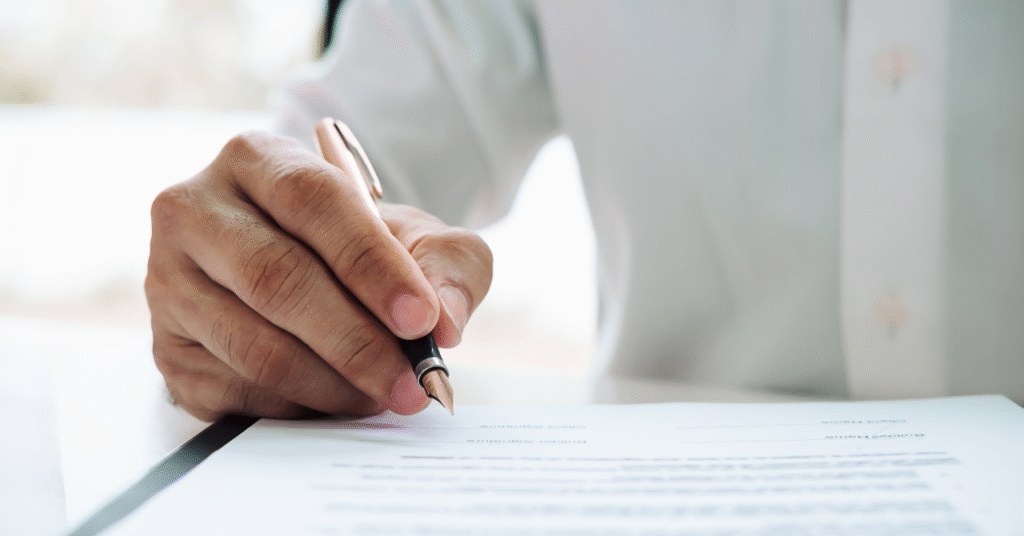
マイナンバー確認書類も、開業届を提出する際に必要です。マイナンバー確認書類として認められるのは、下記の書類です。
- マイナンバーカード
- マイナンバー通知カード
- マイナンバー記載の住民票
- マイナンバー記載の住民票記載事項証明書
- マイナンバー記載の住民税特別徴収税額通知書
- 公的機関発行のマイナンバー確認書類
開業届の提出にe-Tax(電子申告)を利用する場合は、マイナンバーカードとICカードリーダーが必要です。e-Taxでは、マイナンバーカードによる電子署名が求められます。
印鑑
窓口や郵送で開業届を提出する場合は、印鑑の押印が必要です。実印または認印が有効で、シャチハタタイプの印鑑は認められません。印鑑は開業届の「提出者の押印」欄に押印してください。印鑑の大きさに厳密な規定はありませんが、一般的には12〜15mm程度のサイズが適しています。
開業届に押す印鑑は、朱肉を使い、鮮明に押すことが重要です。印鑑の押し忘れがあると、開業届が受理されないため押し忘れのないようにしましょう。
開業届の記入方法

開業届は必要事項の記入漏れや誤字脱字に注意しましょう。訂正は二重線と訂正印で行います。開業届に修正液は使用できません。開業届の必要事項は、下記のとおりです。
- 納税地の税務署名・提出日
- 納税地/上記以外の住所地・事業所等
- 氏名/生年月日/個人番号
- 職業/屋号
- 届出の区分/所得の種類
- 開業・廃業等日
- 事業の概要
- 給与等の支払い状況
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無
納税地の税務署名・提出日
開業届の「納税地の税務署名」には、自分の住所地または事業所の所在地を管轄する税務署の名前を記入してください。どの税務署が自分の地域を管轄しているかわからない場合は、国税庁のWebサイトで簡単に確認できます。「提出日」は、開業届を税務署に提出する年月日を記入しましょう。
開業届の提出日は西暦でなく和暦(令和〇年〇月〇日)で記入します。開業届の提出日は、開業日より前でも後でも問題ありません。納税地が複数ある場合は、主たる事業所がある場所を管轄する税務署を選んでください。
納税地/上記以外の住所地・事業所等

開業届の「納税地」とは、所得税の納税や確定申告書の提出を行う場所です。納税地には主に下記のいずれかを記入してください。
- 自宅で事業を行う場合の自宅住所
- 事務所や店舗の住所
- 複数事業所がある場合の主たる事業所
納税地と実際の住所が異なる場合は「上記以外の住所地・事業所等」に自宅の住所を記入する必要があります。住所と事業所が同じ場所にある場合は空欄のままです。開業届に納税地を記入する際には、番地や部屋番号まで正確に記入しましょう。
開業届に納税地を記入するときは、マンション・アパート名や部屋番号も省略せずに記入する必要があります。郵便番号も忘れずに記入してください。開業届は納税地に記入した住所を管轄する税務署に提出します。引越しなどで納税地が変わった場合は、異動届出書の提出が必要です。
氏名/生年月日/個人番号
開業届の「氏名」には、戸籍上の氏名をフルネームで記入します。氏名の横にはフリガナも忘れずに記入してください。外国籍の場合は、通称名ではなく在留カード等に記載された氏名を記入する必要があります。「生年月日」は西暦または元号のどちらでも記入可能です。
開業届の「個人番号(マイナンバー)」には、12桁のマイナンバーを記入してください。個人番号の記入は任意ですが、記入すると行政手続きがよりスムーズになります。
職業/屋号

開業届の「職業」には、具体的な事業内容を記載してください。IT技術者や飲食店経営、不動産販売業など、税務署が理解しやすい一般的な表現を使うことがポイントです。サービス業などの曖昧な表現は避けましょう。開業届の「屋号」には、事業で使用している名称を記入します。
屋号は「商号」とも呼ばれます。屋号の記入は必須ではありません。複数の業種で事業を行う予定の場合は、主たる業種を記載してください。青色申告承認申請書などの他の書類とも整合性を持たせることも大切です。後から屋号を変更したい場合は「個人事業の開業・廃業等届出書」を再度提出する必要があります。
届出の区分/所得の種類
開業届の「届出の区分」は開業・廃業・変更の中から選びチェックを入れましょう。「所得の種類」は、事業や収入源に合わせて下記から該当するものを選んでください。
- 営業所得
- 農業所得
- 漁業所得
- 不動産所得
- 利子所得
- 配当所得
- 給与所得
- 山林所得
- 譲渡所得
- 一時所得
- 雑所得
複数の所得がある場合は、収入の中で最も大きな割合を占めるものにチェックを入れてください。
開業・廃業等日

開業届の「開業・廃業等日」には、実際に事業活動を始めた日や、初めて事業として収入を得た日などを記入しましょう。記入形式は「令和○年○月○日」または「R○.○.○」のどちらかです。開業届に将来の日付は記入できません。開業日は税務署へ開業届を提出した日から1年以内であれば遡って申告できます。
廃業の場合は、実際に事業活動を終了した日を開業届に記入しましょう。廃業日も税務上重要な日付です。
事業の概要
事業の概要欄に下記の内容を簡潔にまとめて記入してください。
- 提供する商品やサービスの内容
- 主な業務内容や事業活動
- ターゲットとなる顧客層
- 事業の形態
- 事業規模
開業届の「事業の概要」には「Webデザイン・ホームページ制作」など具体的に書きましょう。専門的な技術や資格が必要な事業の場合は、内容を記入するのがおすすめです。将来的な事業拡大の方向性についても簡潔に触れると、事業の全体像を把握しやすくなります。
必要な許認可がある業種の場合は、許可の取得状況や予定についても開業届に記入しましょう。
給与等の支払い状況
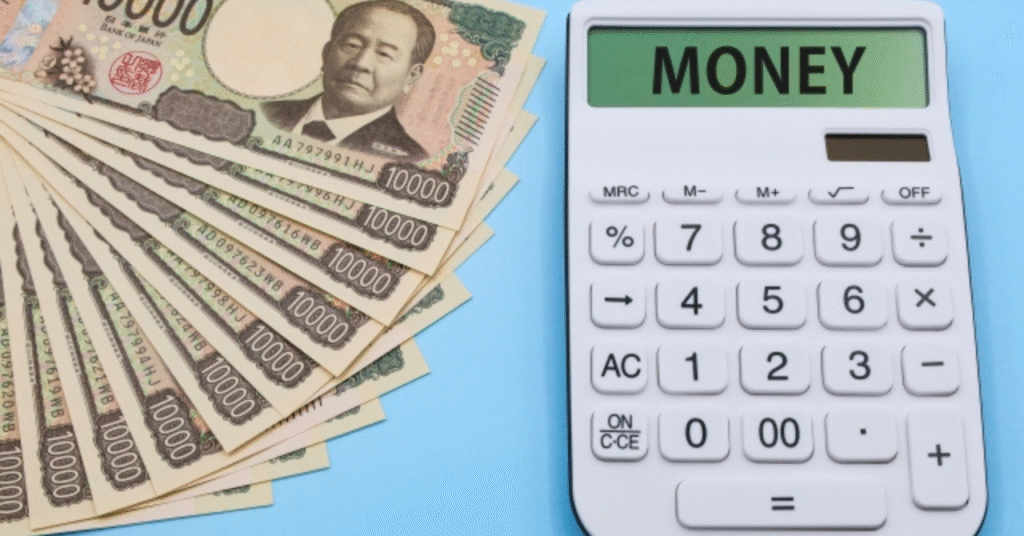
開業届の「給与の支払い状況」では、給与等の支払いがある場合は「有」を、ない場合は「無」を選択してください。給与等の支払いには、正社員だけでなく、アルバイトやパートタイム従業員、家族従業員も含まれます。開業届の「給与の支払い状況」で「有」を選択した場合は源泉徴収義務が発生します。
税務署に「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納付書)」の提出が必要です。別途「給与支払事務所等の開設届出書」も提出しなければなりません。将来的に給与支払いの予定がある場合も「有」を選択するのが一般的です。給与支払いの開始予定日も開業届に記入しましょう。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無
開業届で「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無」は「有」か「無」を選んでください。源泉所得税の納期の特例とは、通常毎月10日までに納付する必要がある源泉所得税を、年2回だけにできる制度です。
「有」を選んだ場合は、開業届と一緒に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」も提出できます。源泉所得税の納期の特例が適用されると、毎月の納付手続きが不要となり、事務作業を効率化できます。開業届で「無」を選んだ場合は、源泉徴収した所得税を翌月10日までに毎月納付しましょう。
開業届の提出方法
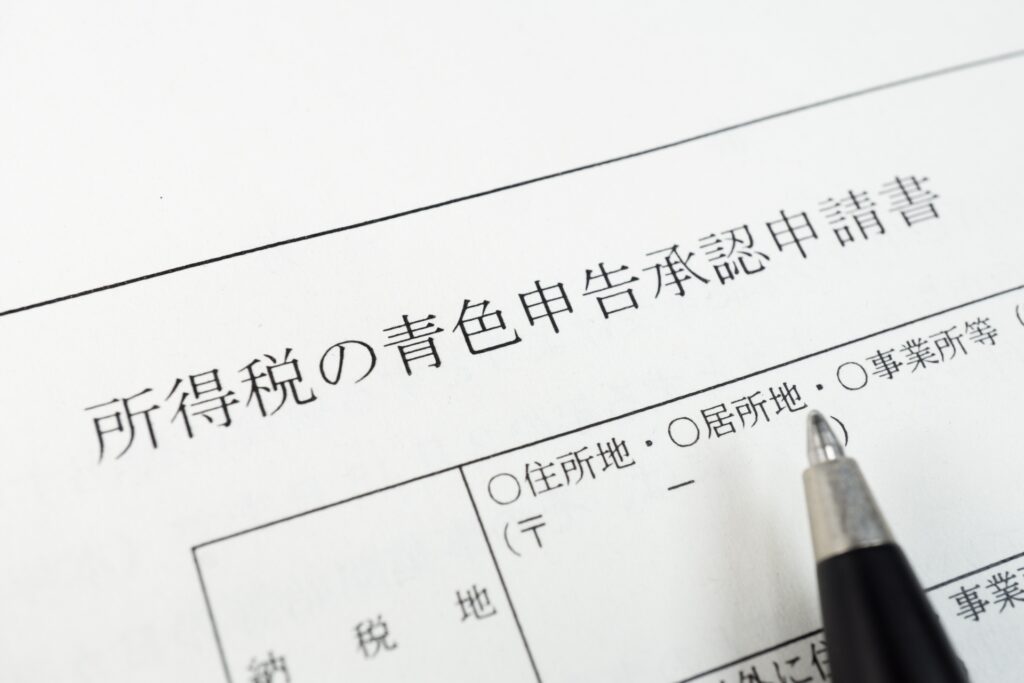
開業届の提出方法は、下記の3種類です。
- 税務署の窓口で提出する
- 郵送で提出する
- e-Tax(電子申告)で提出する
税務署の窓口で提出する
開業届は税務署の窓口でも提出できます。開業届を窓口で提出するメリットは、不備があればすぐに指摘してもらえる点です。税務署の窓口で開業届を提出する手順は下記のとおりです。
- 平日8:30~17:00に税務署を訪問する
- 窓口で必要書類を提出する
- 不備の修正をしてもらう
- 開業届の控えをもらう
開業届を税務署の窓口で提出すると、開業届の控えを事業開始の証明としてすぐに使用できます。開業届の控えは銀行口座開設や各種契約時に必要になるケースが多いので、しっかり保管しましょう。年度初めや確定申告時期の税務署は混雑します。税務署で長時間待つことを避けたい場合は、事前に電話で予約するのがおすすめです。
郵送で提出する

開業届は郵送で提出する方法もあります。記入した開業届と必要書類のコピーを封筒に入れて管轄の税務署宛てに送るだけで手続き完了です。郵送で開業届を提出する際の提出日は、税務署に届いた日付になります。開業日から1か月以内に届くよう余裕を持って送付しましょう。
開業届を郵送で提出する際は、必ず返信用封筒も同封してください。後日税務署から受領印を押した開業届の控えが返送されます。開業届の控えは大切な書類です。必ず安全な場所に保管してください。
e-Tax(電子申告)で提出する
e-Tax(電子申告)で開業届を提出する方法もあります。自宅や事業所から24時間365日いつでも開業届の提出が可能です。e-Tax(電子申告)で開業届を提出するには、マイナンバーカードとICカードリーダーが必要です。ICカードリーダーの代わりにマイナポータルと連携して開業届を提出できます。
e-Tax(電子申告)は税務署に行く必要がなく、添付書類もデータでアップロードできることが魅力です。入力ミスがあるとエラーメッセージが表示されるので、記入漏れや間違いを防げます。開業届の提出後は自動で受付完了のお知らせが届き、処理状況もオンラインで確認可能です。
開業届の提出に必要なものに関するよくある質問
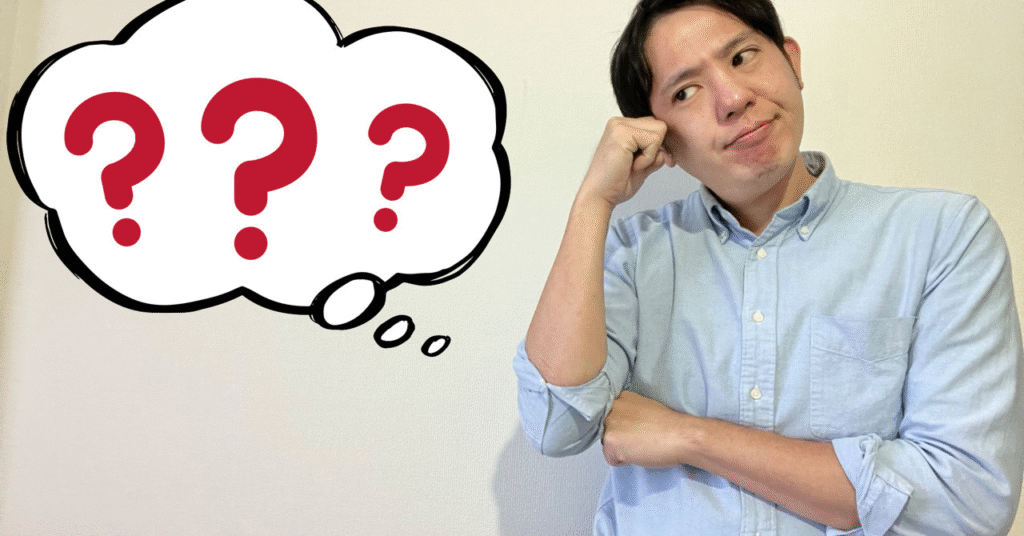
開業届の提出に必要なものに関するよくある質問を紹介します。
- 開業届はどこで取得できる?
- 開業届の控えを紛失した場合の対処法は?
- 開業届以外に必要な書類は?
開業届はどこで取得できる?
開業届の取得方法は、下記のとおりです。
- 最寄りの税務署の窓口
- 国税庁のWebサイト
- e-Tax
- 税理士事務所
- 法人設立ワンストップサービス(法人向けのサービスのため、個人事業主には通常不要)
市区町村役場やコンビニのマルチコピー機から、開業届の取得はできないため注意しましょう。開業届の記入方法に不安がある場合は、税務署の窓口で相談するとアドバイスがもらえます。

開業届の控えを紛失した場合の対処法は?
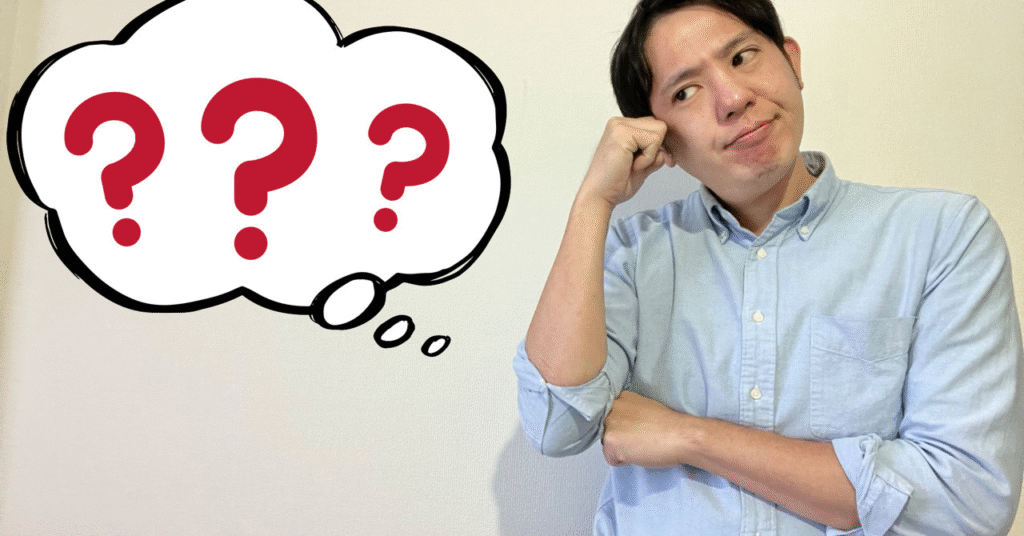
開業届の控えを紛失した場合は、税務署で「開業届」の写しを請求できます。税務署に直接行って「開業届」の写しを請求しましょう。「開業届」の写しを請求する際には、本人確認書類の提出が必要です。スムーズに手続きを進めるために、事前に電話で税務署に問い合わせることをおすすめします。
「開業届」の写しは、手数料はかからないのが一般的です。開業届の提出から長い時間が経過している場合は、税務署での保管期間を過ぎている可能性もあるため注意してください。e-Tax(電子申告)で開業届を提出した場合は、e-Taxのメッセージボックスから再取得できます。
引っ越しなどで管轄の税務署が変わっている場合は、現在の管轄税務署に問い合わせましょう。
開業届以外に必要な書類は?
個人事業主として開業する際に、開業届以外に必要な可能性がある書類は、下記のとおりです。
- 個人事業開始申告書
- 青色申告承認申請書
- 国民健康保険・国民年金の切り替え手続き
業種によっては屋号・商標登録や保険加入なども検討しましょう。
まとめ

開業届を提出する際には、本人確認書類、マイナンバー確認書類、印鑑の3点が必要です。開業届は自分の状況に応じて最も便利な方法を以下から選んで提出しましょう。
- 税務署の窓口で提出する
- 郵送で提出する
- e-Tax(電子申告)で提出する
記事で紹介した必要な準備をしっかり行い、スムーズに開業手続きを進めてください。


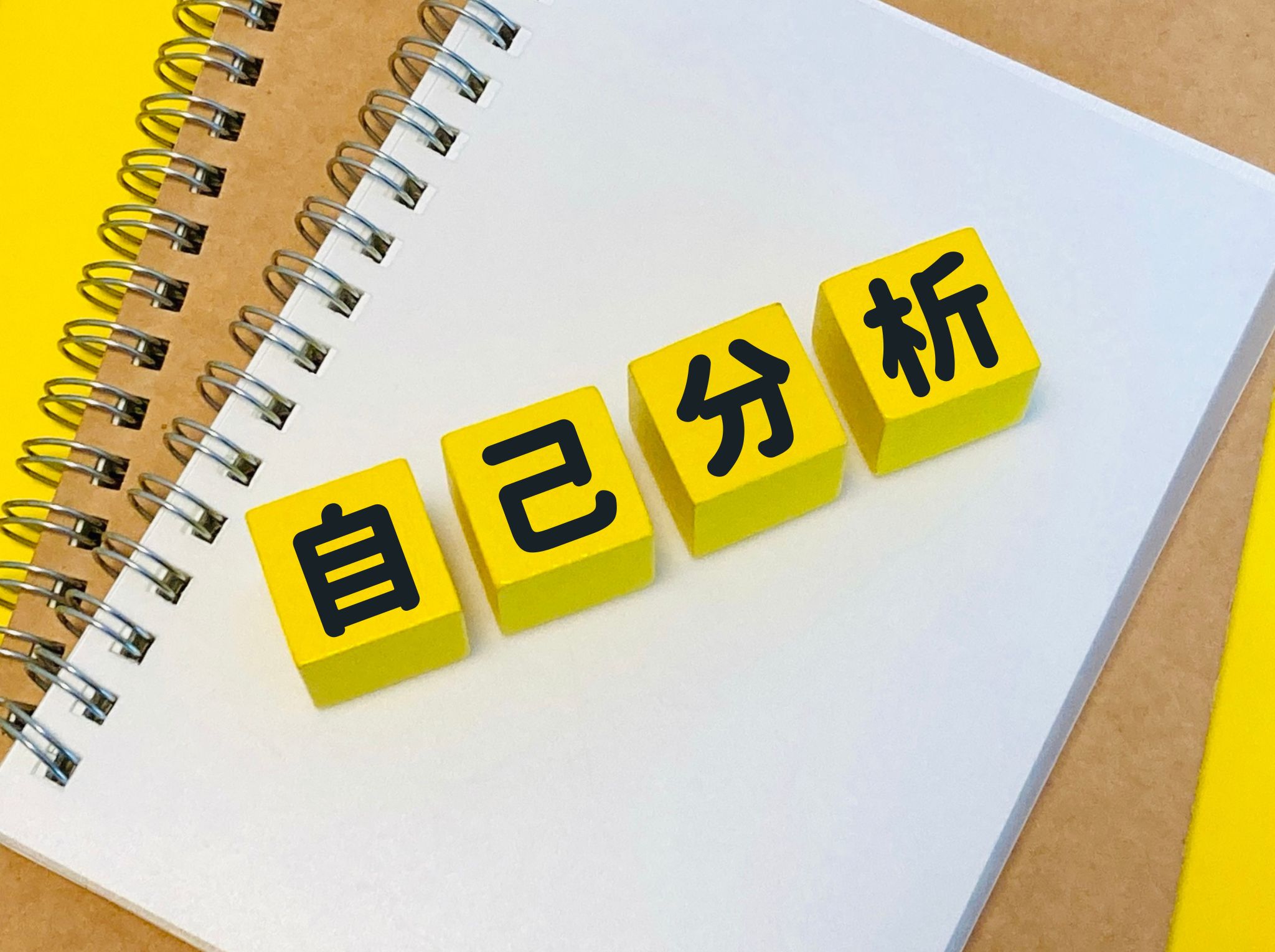


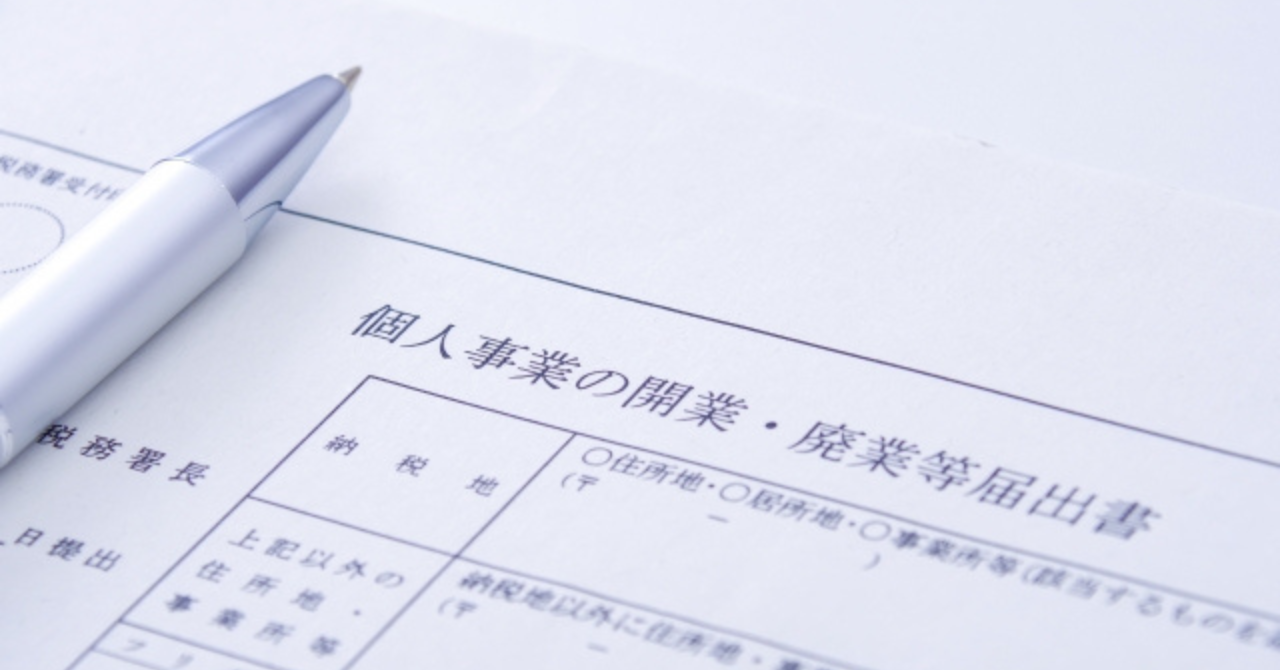

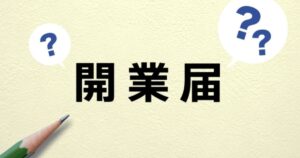
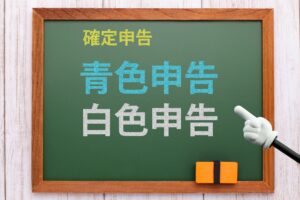



コメント