独立・開業を考えているものの、手続きが複雑そうで踏み出せずにいる方は多くいます。この記事では、開業届の入手方法や記入欄ごとの書き方、提出方法を詳しく解説します。記事を読めば、開業届の書き方のポイントがわかり、安心して開業することが可能です。
開業届を書く前の基礎知識
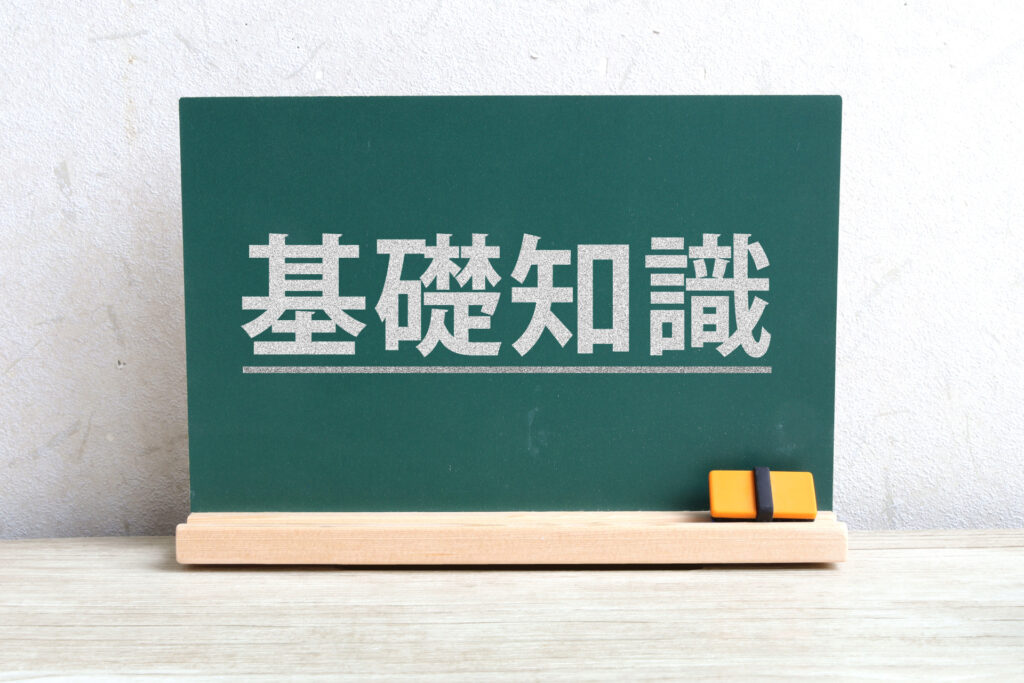
開業届は、個人事業主が事業開始時に税務署へ提出する書類です。開業届は事前提出も可能で費用はかかりません。開業届の入手方法と開業届を書く際に必要なものについて、詳しく解説します。

開業届の入手方法
開業届は税務署の窓口で入手できます。税務署の窓口では担当者に相談しながら開業に必要な書類を受け取れるため、初めて開業する方でも安心して準備を進められます。時間や場所の都合が合わない場合は、インターネットを使って開業届を入手しましょう。
国税庁のウェブサイトから開業届の用紙をPDF形式でダウンロード可能です。自宅のプリンターで開業届を印刷する際は用紙サイズや印刷設定に注意してください。開業届は提出期限があるので、余裕をもって入手しましょう。

開業届を書く際に必要なもの
スムーズに手続きを進めるため、開業届を書く際には必要な書類や情報を事前に準備しておくことが重要です。開業届の記入に必要なものは、以下のとおりです。
- マイナンバー
- 印鑑
- 屋号の情報
- 事業所の住所・連絡先
印鑑にシャチハタは使用できないため、注意してください。事業内容や開業日がわかる資料なども準備しておくと記入がスムーズです。青色申告を希望する場合は青色申告承認申請書、従業員を雇用する予定がある場合は従業員情報が必要です。

開業届の書き方
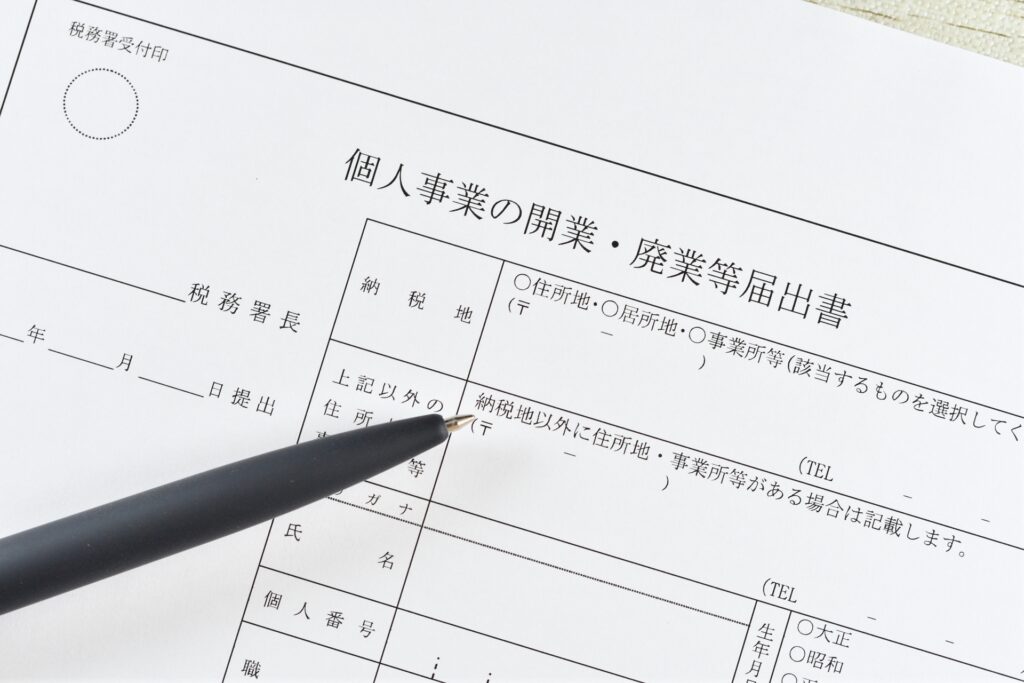
開業届には多くの記入欄があります。開業届の以下の項目の書き方について、詳しく解説します。
- 提出日
- 納税地/上記以外の住所地・事業所等
- 氏名/生年月日/マイナンバー
- 職業
- 屋号
- 届出の区分
- 所得の種類
- 開業・廃業等日
- 開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
- 事業の概要
- 給与等の支払いの状況
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無
- 給与支払を開始する年月日
提出日
開業届の提出日欄には、実際に税務署へ提出する日付を記入してください。郵送の場合は投函した日が提出日となり、e-Taxで電子申請する場合は送信した日が提出日です。
納税地/上記以外の住所地・事業所等
納税地とは、税金を納める場所のことです。納税地は原則住所地ですが、事業所等が住所地と異なる場合は、納税地を選択可能です。住所地を納税地とする場合は「住所地」にチェック、事業所等を納税地とする場合は「事業所等」にチェックします。
納税地にしなかった住所や事業所は「上記以外の住所地・事業所等」欄に記入しましょう。複数の事業所がある場合は、主たる事業所を納税地とするのが一般的です。開業届を記入する際は、郵便番号も忘れずに記載し、建物名やマンション名、部屋番号まで正確に記入しましょう。
氏名/生年月日/マイナンバー

開業届の氏名欄は、楷書体でフルネームを正確に記入してください。旧字体などの特殊な漢字を使用している場合でも、戸籍上の表記どおりに記入しましょう。外国籍の方はアルファベット表記での記入も可能です。開業届の生年月日欄は、元号または西暦のどちらでも記入できます。
開業届のマイナンバー欄は、12桁の番号を間違いなく記入してください。マイナンバーは、マイナンバーカードや通知カード、マイナンバー入りの住民票などで確認できます。
職業
開業届の職業欄には、会計士やコンサルタント、デザイナーなど、一般的に認識されている職業名を簡潔に記載しましょう。曖昧な表現や抽象的な記載は避け、実際に行う業務内容に即した職業名を選びます。複数の事業を行う予定がある場合は、主となる事業を記入してください。
Webデザインと写真撮影の両方を行う場合には、収入の比重が大きい方や中心となる事業を開業届に記載しましょう。医師や弁護士など法律で定められた資格が必要な職業は、資格を取得してからでないと開業届に記入できないため注意してください。
開業届の職業欄の記載内容は、所得区分の判断材料にもなります。将来的に事業内容が変わった場合には、変更届を提出する必要があります。
屋号

屋号とは、自分の事業を表す名称のことです。屋号は必須ではなく、個人の名前だけで事業を行うことも可能です。屋号がない場合は、開業届の屋号の欄を空白のままにしておいても問題ありません。一般的な屋号の例には、以下のようなものがあります。
- ○○商店
- △△事務所
- □□工房
- ××デザイン
開業届に記入する際は、商品やサービスの提供内容が伝わりやすい屋号にしましょう。屋号は後からでも変更できますが、取引先や顧客に混乱を招かないよう慎重に選ぶことがおすすめです。
届出の区分
開業届の届出の区分には、以下の3つの選択肢があります。
- 新規開業
- 再開業
- その他
初めて事業を始める場合は新規開業、廃業した事業を再び始める場合は再開業の区分に「○」を記入してください。「その他」は事業内容の変更や住所変更などの場合に選択します。複数の事業を同時に行う予定がある場合は、主たる事業について開業の届出を行いましょう。
所得の種類

税金計算や確定申告のため、事業活動によって発生した収入は、主に以下の10種類の所得に分けられます。
- 事業所得
- 不動産所得
- 利子所得
- 配当所得
- 給与所得
- 退職所得
- 山林所得
- 譲渡所得
- 一時所得
- 雑所得
事業所得は自営業やフリーランス、コンサルタントなどの事業活動から生じる所得です。不動産所得は土地・建物などの貸付けからの収入、雑所得は副業や原稿料、講演料などからの収入が該当します。所得の種類によって、税金の計算方法や必要な経費の範囲が異なります。
開業・廃業等日
開業・廃業等日の欄には、事業を実際に開始した日付または終了した日付を正確に記入する必要があります。まだ開業していない場合は、開業予定日を記入してください。開業日が明確でない場合は、事業用の経費を支出した日や初めて売上が発生した日を目安にします。
開業届は事業開始から1か月以内の提出が望ましいですが、開業日を遡って申告することも可能です。複数の事業を同時に始める場合は、最初に開始する事業の日付を記入します。廃業の場合は、実際に事業活動を終了した日付を記入してください。
開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
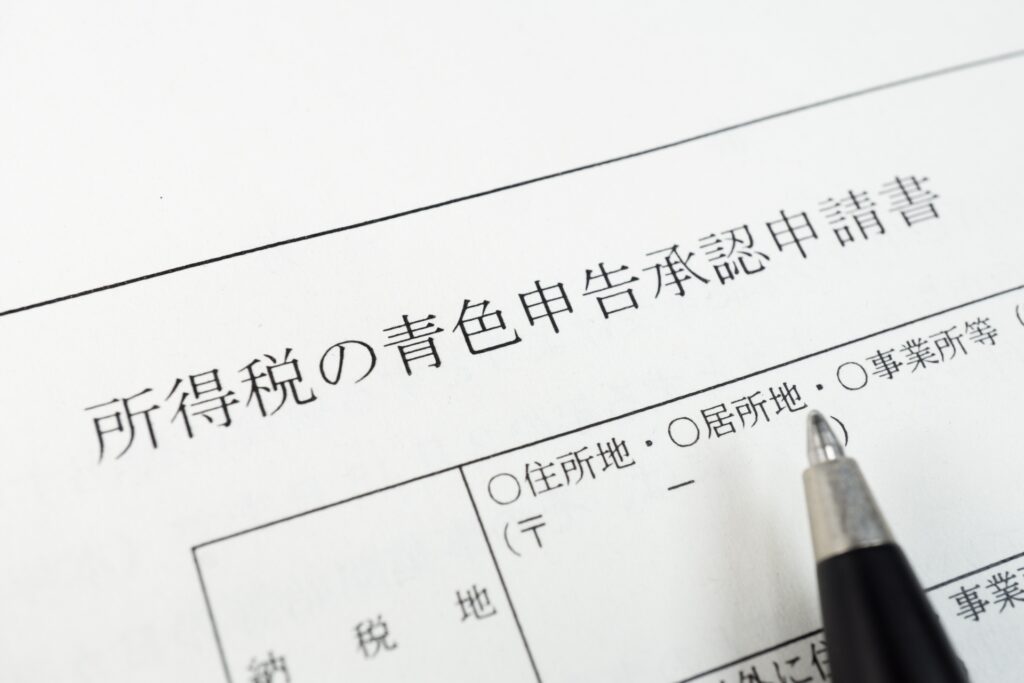
開業届には開業・廃業に伴う届出書の提出の有無の項目があります。税務署へ提出する各種届出書について「有」か「無」を選択してください。主な届出書には以下のようなものがあります。
- 青色申告承認申請書
- 給与支払事務所等の開設届出書
- 消費税課税事業者選択届出書
青色申告で確定申告を行いたい場合は「青色申告承認申請書」の欄を「有」にしてください。さまざまな税制上の優遇措置があるので、多くの個人事業主は青色申告を行っています。従業員を雇用する予定がある場合は「給与支払事務所等の開設届出書」の欄を「有」にしてください。
消費税の課税事業者になる場合は「消費税課税事業者選択届出書」の欄を「有」にしましょう。売上規模によっては、消費税の納税義務が発生しないこともあります。自分の事業が課税事業に該当するかが不明な場合は、税務署や税理士に相談しましょう。
事業の概要
開業届では事業の概要を明確に記載することが重要です。一般的な業種名だけを書くのではなく、実際に行う業務内容を詳しく記載してください。事業の概要は以下のように具体的に書く必要があります。
- Webサイト制作サービス
- スマートフォンアプリ開発
- ITコンサルティング業務
主な取扱商品やサービスも明記すると、事業内容がより明確になります。複数の事業を行う予定がある場合は、主たる事業を記載した後に副業的な事業を書きましょう。将来的に事業拡大の可能性があっても、開業届には現時点で始める予定の事業内容を記載してください。
記入欄のスペースが足りない場合は、別紙を添付して詳細を説明することも可能です。
給与等の支払いの状況

給与等の支払いの状況の欄は「1. 給与等の支払いがある」と「2. 給与等の支払いがない」のどちらかに〇をつけてください。税務上の手続きに大きく影響するため、給与等の支払いの有無は慎重に判断しましょう。「1. 給与等の支払いがある」に該当する主なケースは、以下のとおりです。
- 従業員を雇用している場合
- 今後、従業員を雇用する予定がある場合
- 家族従業員に給与を支払う場合
- アルバイトやパートタイマーを雇う場合
「2. 給与等の支払いがない」を選ぶのは、個人事業主のみで事業を行い、他に給与を支払う相手がいない場合です。「1」を選択した場合は、追加で「給与支払事務所等の開設届出書」が必要になるので、提出を忘れないようにしましょう。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無
源泉所得税の納期の特例とは、通常毎月納付が必要な源泉所得税を年2回の納付にできる便利な制度です。常時10人未満の従業員に給与を支払っている小規模な事業者が対象です。源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出が「有」の場合は、「提出済」か「提出予定」かを選ぶ必要があります。
開業届の提出時点で、申請書を提出している場合は「提出済」に、これから提出する場合は「提出予定」にチェックを入れましょう。開業届を提出する時点で申請していなくても、後日「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を別途提出できます。
給与支払を開始する年月日
開業届の給与支払を開始する年月日は、従業員に初めて給与を支払う予定日を記入する欄です。開業時に従業員がいない場合は空欄で良いですが、将来的に従業員を雇う予定がある場合は、雇用開始予定日を記入します。既に従業員に給与を支払っている場合は、最初に給与を支払った日付を記入してください。
家族従業員へ給与を支払う場合も、開業届に給与支払を開始する年月日を忘れずに記載しましょう。給与支払を開始する日付は、源泉所得税の納付義務が発生する基準日となるため、正確に記入することが大切です。給与支払開始日が確定していない場合には、予定日を記入して後日変更することも可能です。
開業届の出し方
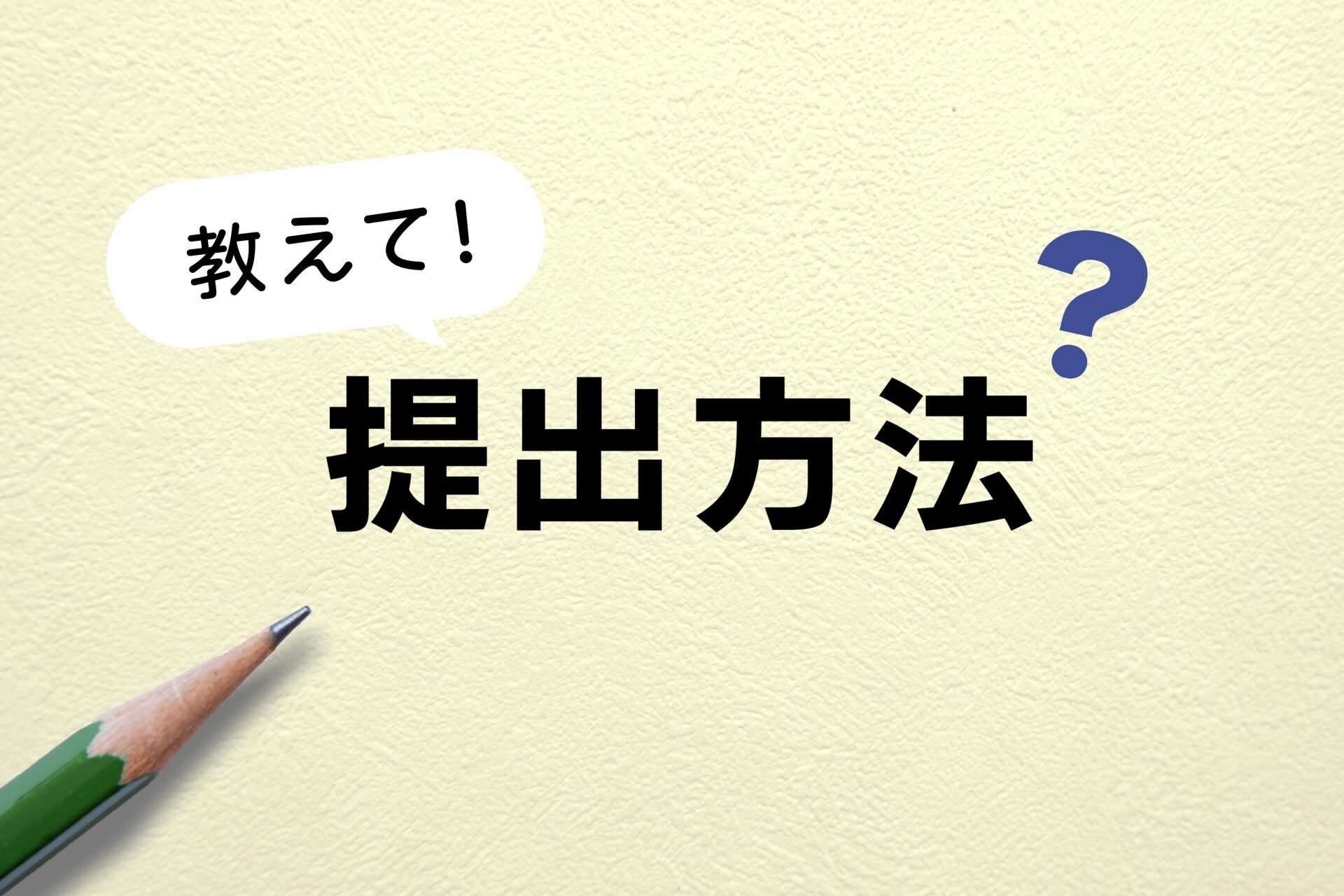
開業届の提出について、押さえておくべき点は以下のとおりです。
- 開業届の提出先と期限
- 開業届の提出時に必要なもの
- 開業届の提出方法
開業届の提出先と期限
開業届は、事業を始めた後1か月以内に税務署へ提出する必要があります。提出先は、事業所または自宅の所在地を管轄する税務署です。期限内に提出することが法律上の義務ですが、提出が遅れても罰則はありません。複数の事業所を持っている場合は、主たる事業所を管轄する税務署に提出してください。
開業届は、開業前でも提出可能です。青色申告を希望する場合は、開業から2か月以内に青色申告承認申請書も合わせて提出する必要があります。
開業届の提出時に必要なもの

開業届を提出する際には、以下の書類を用意しましょう。
- 開業届の記入済み用紙
- 本人確認書類
- マイナンバー確認書類
- 印鑑
- 委任状
開業届を提出する際の本人確認書類には運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなどが使えます。印鑑は認印で問題ありません。特定の業種では、開業届を提出する際に事業に関する資格証明書などが求められる場合があります。
開業届の提出方法
開業届の主な提出方法は、以下のとおりです。
- 税務署窓口への直接提出
- 郵送による提出
- e-Taxによる電子申請
開業届を税務署へ直接持参する場合は、平日の8:30〜17:00の間に窓口へ行きましょう。提出時には必ず身分証明書やマイナンバーカードなどの必要書類を持参してください。控えを用意して受付印をもらっておくと安心です。代理人が開業届を提出する場合は、委任状が必要になるので注意してください。
税務署へ行く時間がない方は、記入済みの開業届を管轄の税務署へ郵送で提出しましょう。e-Taxによる開業届の電子申請では、マイナンバーカードまたはIDとパスワードが必要です。e-Taxを使えば、インターネットを通じて24時間いつでも開業届を提出できます。
開業届を出す際の注意点

開業届を提出する際の注意点は、以下のとおりです。
- 開業届以外に提出が必要な書類を確認する
- 確定申告の必要性を理解する
開業届以外に提出が必要な書類を確認する
開業届を提出するだけでは開業の手続きは完了しません。事業の形態や状況に応じて、以下のような書類が必要になる場合があります。
- 青色申告承認申請書
- 所得税の棚卸資産の評価方法の届出書
- 減価償却資産の償却方法の届出書
- 給与支払事務所等の開設届出書
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
- 青色事業専従者給与に関する届出書
事業とは別に個人として行う手続きも忘れないようにしましょう。国民健康保険への加入手続きは市区町村役場で、国民年金保険料の納付手続きは年金事務所で行ってください。
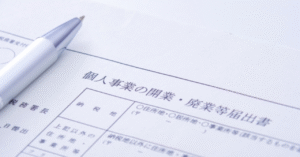
確定申告の必要性を理解する
開業届を提出した後は、原則、毎年確定申告を行う必要があります。確定申告とは、1年間の所得と税金を計算して申告する手続きです。年間の所得が48万円を超える場合は、確定申告の義務が生じます。確定申告の期間は、翌年の2月16日〜3月15日です。
確定申告には青色申告と白色申告の2種類があり、青色申告を選ぶと最大65万円の控除が受けられます。青色申告をするには、開業から2か月以内に「青色申告承認申請書」の提出が必要です。確定申告では事業所得や経費、控除などの正確な申告が求められます。領収書などの証拠書類は7年間保存する義務があります。
確定申告を怠ると、延滞税や無申告加算税などのペナルティが発生するリスクがあるので注意してください。e-Taxを利用したオンラインでの確定申告が便利なため、積極的に活用しましょう。

まとめ

開業届は個人事業主として活動を始める際に必要な重要な手続きです。開業届は税務署や国税庁のウェブサイトから入手でき、記入には身分証明書や印鑑などの準備が必要です。開業届の事業内容や開業日は明確に記載し、給与支払いに関する内容も適切に申告してください。
開業届の提出先は管轄の税務署で、開業から1か月以内の提出が必要です。確定申告の提出方法には税務署への持参や郵送、e-Taxによる電子申請があります。業種によっては開業届以外の申請も必要になることがあります。不明な点がある場合は税務署に確認し、スムーズに開業届を提出しましょう。


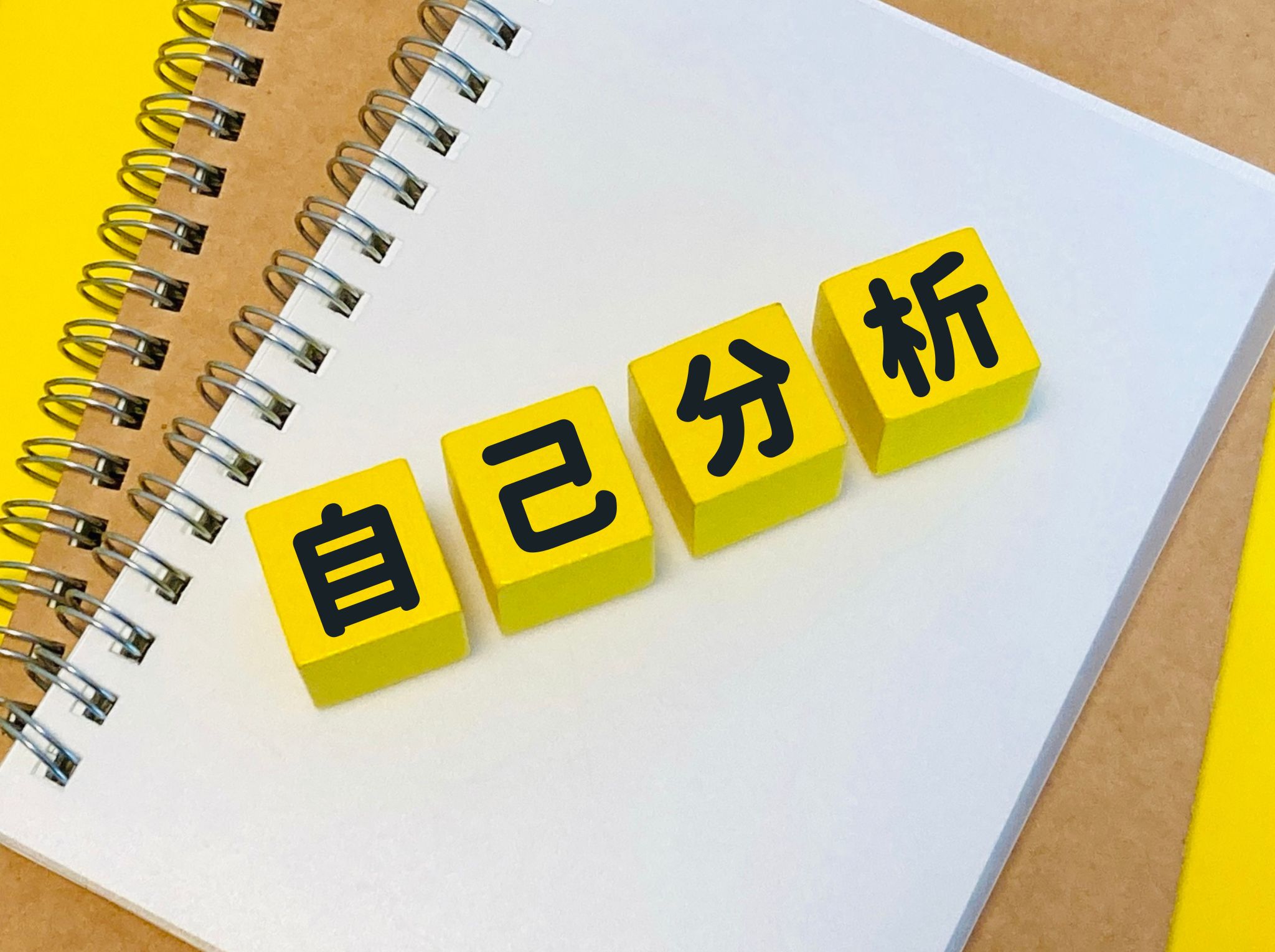


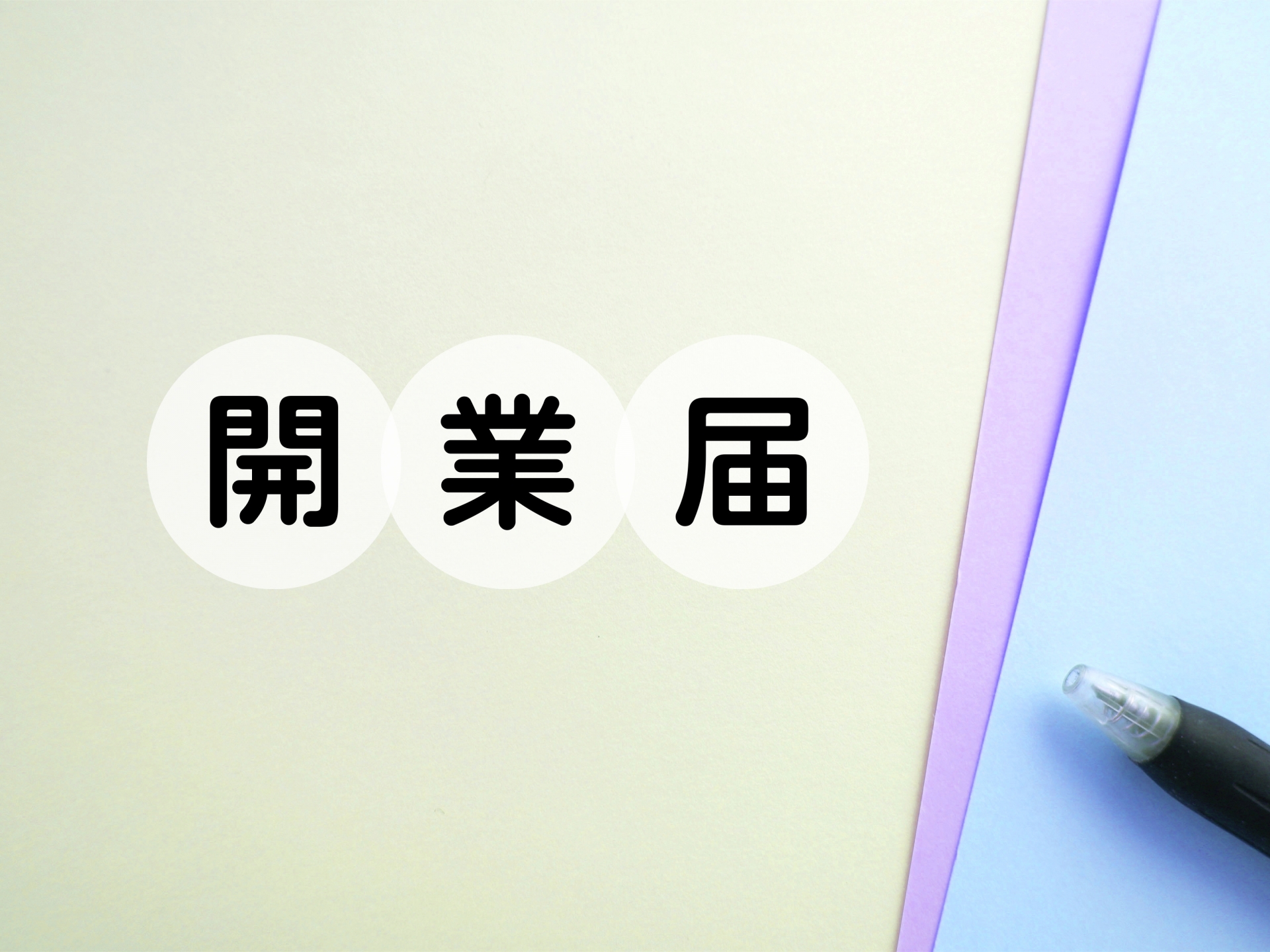

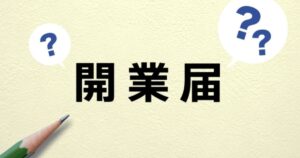
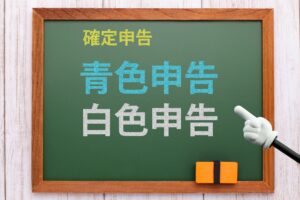



コメント